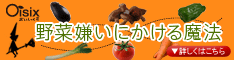 �@
�@ �@
�@ �@
�@�@BCAA
�@BCAA�́ABranched Chain Amino Acid�i���A�~�m�_�j�̗��ŁA���C�V���A�C�\���C�V���A�o�����̂R��ނ̃A�~�m�_������B
�@BCAA�́ABCAT���A��-�P�g�O���^���_�Ɣ������A�A�����j�A�����ɕK�v���O���^�~���_���A���������B
�@�^�����ɁABCAA����́A�A�����j�A�iNH3�j����������̂ɕK�v���O���^�~���_���A����������B
�@���i�ŁABCAA�̑�ӂŎY�������L�łȃA�����j�A�́ABCAT�ɂ�薳�Q�ȃO���^�~���_�ɕϊ�����A����ɁA�O���^�~�������y�f�ɂ���O���^�~���ɕϊ������B
�@BCAA�́A���i��]�ő�ӂ���A���������O���^�~����A�A���j���́A���t����A������A�t���⏬���ŁA��ӂ����B�܂��A�O���^�~����A���j���́A�̑���ɗA������A�A�����j�A�����������A�f��H��A���V���̌o�H�ɁA�g�p�����B
�@AAA��`�I�j���́A��ɁA�̑��ő�ӂ����B
�@�̕s�S�i���NJ̉����㏞���̍d���j�ł́A�����A�~�m�_�Z�x���ω����āABCAA�iVal�ALeu�AIle�j�Z�x���ቺ���AAAA�iTyr�APhe�ATrp�j�Z�x��A���`�I�j���iMet�j�Z�x���A��������B
�@�P�DBCAA�́A���i�ő�ӂ����
�@BCAA�́ABranched Chain Amino Acid�i���A�~�m�_�j�̗��ŁA���C�V���A�C�\���C�V���A�o�����̂R��ނ̃A�~�m�_������B
�@ ���C�V���A�C�\���C�V���A�o�����̂R��ނ��A�~�m�_�́ABCAA�iBranched Chain Amino Acid�F���A�~�m�_�A���}�A�~�m�_�j�Ƒ��̂����B
�@BCAA�́A�������̗V���K�{�A�~�m�_�̖�S�����߂Ă���B
�@BCAA�́A�̑��ł͂قƂ�Ǒ�ӂ��ꂸ�A��Ƃ��āA���i�Ɣ]�ő�ӂ����B
�@BCAA�́A���i�̒`���������𑣐i���A�`�����̕�����}������B
�@BCAA�́A�^�����̍��i�̈ێ���ʂɁA�d�v�Ȗ���������ƌ�����B
�@BCAA�́A�^����̋ؓ��̔�J���A�����ɁA������i�^���R����A�S����̋ؓ��ɂ��J�����A�����A�y������j�B�^�����ɁA�ؓ��ɃO���R�[�Q�����s������ƁA�ؓ��̒`�����̃A�~�m�_����������G�l���M�[���ƂȂ邪�ABCAA�́A�G�l���M�[���ƂȂ�A�ؓ��̒`�����̃A�~�m�_�̕�����}�����i��J�����Ȃ��j�A�܂��ABCAA�́A�ؓ��̍����𑣐i������i��J�𑣐i������j�B
�@BCAA�i�̃T�v�������g�j�́A�P���A�Q�`�Sg�A�^���O���^������ɁA���p����B
�@BCAA�𑽂��܂ސH�i�ɂ́A�哤�ށA�����i�������j�A�}�O���i�Ԑg�j�A���炱�A�`�[�Y�A�����Ȃǂ�����B
�@�e�H�i�Ɋ܂܂��BCAA�ʂ��A�ܒ��H�i�����\�Q�O�O�T�Œ��ׁA�\�P�ɂ܂Ƃ߂��B�\�P�ŁABCAA�����A�~�m�_�AAAA���F�����A�~�m�_�AVal���o�����ALeu�����C�V���AIle���C�\���C�V���APhe���t�F�j���A���j���ATyr���`���V���ATrp���g���v�g�t�@���AAla���A���j���AGlu���O���^�~���_�AMet�����`�I�j�����Ӗ�����B�Ȃ��A�F�����A�~�m�_�iAAA�j�̍��̍��v�ʂŁA*�����t���ɕ\�������H�i�́A�ܒ��H�i�����\�Q�O�O�T�ŁA�F�����A�~�m�_�iAAA�j�̍��v�ʂ��A�t�F�j���A���j���iPhe�j�ƁA�`���V���iTyr�j�̐��l�𑫂����l�ƈقȂ��Ă���B
�@������A�哤�H�i�i�ؖȓ����Ȃǁj�́A���`�I�j���ܗʂ����Ȃ��B�\1�ɂ͎����Ȃ����A���ނ́A�̑��a�ɗǂ��^�E�����𑽂��܂�ł���B
�@���L�\�P��BCAA/AAA��̓��Amg���BCAA��AAA�iPhe�{Tyr�{Trp�j��mg��AFischer���BCAA��AAA�iPhe�{Tyr�j�̃�����i���q�ʁFVal���P�P�V�ALeu���P�R�P�AIle���P�R�P�APhe���P�U�T�ATyr���P�W�P�j���L�����B
�@�\�P�@�H�i����BCAA�ܗ��i�H��100g������̊ܗʁF�ܒ��H�i�����\�Q�O�O�T�����p�j �@�H�i�� �@�`�����@ �@���A�~�m�_�iBCAA�j �@�F�����A�~�m�_�iAAA�j �@�@BCAA/AAA�� �@���̑� �@Val �@Leu �@Ile �@���v �@Phe �@Tyr �@Trp �@���v �@mg�� �@Fischer�� �@Ala �@Glu �@Met �@�@�@g �@�@mg �@mg �@mg �@mg �@mg �@mg �@mg �@mg �@ratio �@ratio �@mg �@mg �@mg �@�����[�� �@�@16.5 �@ 830 �@1300 �@ 760 �@2890 �@ 870 �@ 680 �@240 �@1790 �@1.615 �@2.528 �@ 680 �@3200 �@260 �@�ؖȓ��� �@�@ 6.8 �@ 380 �@ 600 �@ 370 �@1350 �@ 390 �@ 290 �@100 �@ 780 �@1.731 �@2.686 �@ 320 �@1300 �@100 �@���蓤�� �@�@50.2 �@2900 �@4600 �@2800 10300 �@3000 �@2200 �@760 �@5960 �@1.728 �@2.679 �@2400 �@9700 �@790 �@������ �@�@ 6.8 �@ 430 �@ 570 �@ 290 �@1290 �@ 370 �@ 280 �@ 99 �@ 749 �@1.722 �@2.702 �@ 390 �@1300 �@170 �@�H�p���s�� �@�@ 8.4 �@ 400 �@ 660 �@ 340 �@1400 �@ 460 �@ 240 �@ 96 �@ 796 �@1759 �@2.687 �@ 270 �@3100 �@150 �@���ǂ� �@�@ 6.8 �@ 300 �@ 510 �@ 260 �@1070 �@ 370 �@ 200 �@ 75 �@ 645 �@1.659 �@2.522 �@ 260 �@2600 �@120 �@������ �@�@19.8 �@1100 �@1500 �@ 840 �@3440 �@1000 �@ 770 �@370 �@2170* �@1.585 �@2.643 �@1000 �@4000 �@720 �@����ܐ� �@�@20.6 �@1100 �@1600 �@ 950 �@3650 �@ 830 �@ 690 �@230 �@1730* �@2.110 �@3.265 �@1200 �@2800 �@660 �@�܂���Ԑg�� �@�@28.3 �@1400 �@2100 �@1300 �@4800 �@1000 �@ 920 �@320 �@2220* �@2.162 �@3.403 �@1500 �@3700 �@810 �@�Ђ��� �@�@18.2 �@ 870 �@1300 �@ 770 �@2940 �@ 650 �@ 500 �@200 �@1400* �@2.100 �@3.467 �@1100 �@2500 �@440 �@��{�ނ˔�Ȃ� �@�@22.9 �@1200 �@1900 �@1200 �@4300 �@ 960 �@ 820 �@280 �@2080* �@2.067 �@3.278 �@1400 �@3700 �@660 �@��{������Ȃ� �@�@18.0 �@ 920 �@1500 �@ 880 �@3300 �@ 740 �@ 620 �@210 �@1610* �@2.050 �@3.291. �@1100 �@2900 �@530 �@�{���S���� �@�@12.3 �@ 830 �@1100 �@ 680 �@2610 �@ 640 �@ 500 �@190 �@1290* �@2.023 �@3.114 �@ 700 �@1600 �@400 �@�������� �@�@ 2.9 �@ 190 �@ 280 �@ 150 �@ 620 �@ 140 �@ 110 �@ 38 �@ 288 �@2.153 �@3.369 �@�@93 �@ 560 �@ 75 �@�v���Z�X�`�[�Y �@�@22.7 �@1600 �@2300 �@1200 �@5100 �@1200 �@1300 �@290 �@2790 �@2.153 �@2.794 �@ 670 �@5000 �@580 �@���炱�� �@�@24.9 �@1600 �@2500 �@1500 �@5600 �@1000 �@1100 �@300 �@2400 �@2.333 �@3.642 �@1900 �@3200 �@560 �@�����ݐ� �@�@ 6.8 �@ 360 �@ 460 �@ 300 �@1120 �@ 280 �@ 220 �@ 90 �@ 590 �@1.898 �@3.048 �@ 540 �@ 830 �@180 �@�ق������ �@�@ 3.3 �@ 120 �@ 170 �@�@95 �@ 385 �@ 120 �@�@88 �@ 53 �@ 263* �@1.464 �@2.512 �@ 110 �@ 300 �@ 29 �@*�F�F�����A�~�m�_�iAAA�j�̍��̍��v�ʂŁA*�����t���ɕ\�������H�i�́A�ܒ��H�i�����\�Q�O�O�T�ŁA�F�����A�~�m�_�iAAA�j�̍��v�ʂ��A�t�F�j���A���j���iPhe�j�ƁA�`���V���iTyr�j�̐��l�𑫂����l�ƈقȂ��Ă���B
�@�Ȃ��A���t���̃A�~�m�_�𑪒肵�ċ��߂��ABCAA��AAA�̃�����i����BCAA/AAA��j�́A�t�B�b�V���[��ƌĂ��B�̍d�ϊ��҂ł́A�t�B�b�V���[�䂪�ቺ����i�g���v�g�t�@���Ȃǂ�AAA���A�����ɑ�������j�B �@�Q�DAAA�́A�̑��ő�ӂ����
�@�Q�DAAA�́A�̑��ő�ӂ����
�@�C���X�����́ABCAA�̍��i�ւ̎�荞�݂𑣐i���邪�A�]���̐_�o�`�B�����̑O��̂ɂȂ�A�F�����A�~�m�_�iaromatic amino acids�FAAA�j�̎�荞�݂ɂ́A���܂�e�����Ȃ��B�@
�@AAA�ɂ́A�_�o�`�B�����̑O��̂ł���A�g���v�g�t�@���i�s�����F���P�j�A�t�F�j���A���j���iPhe�j�A�`���V���iTyr�j������B�g���v�g�t�@���i�s�����j�ƃt�F�j�[���A���j���iPhe�j�́A�K�{�A�~�m�_�����A�`���V���iTyr�j�́A�t�F�j�|���A���j���iPhe�j��萶�������B
�@���i�ő�ӂ����BCAA�ƈقȂ�AAAA�́A�A���u�~���ƌ�������ӓI�Ɉ��肵�Ă���g���v�g�t�@���ȊO�́A�̑��ő�ӂ����B
�@�̑��a�̐l�́A�i���b��S�������j���ނ⋛���A�iBCAA�𑽂��܂ށj�哤���i�A���A�����i��ۂ邱�Ƃ����߂��Ă���B
�@BCAA��AAA�̂s�����Ƃ́A�]�ւ̎�荞�݁i�]���t�֖�̒ʉ߁j���A���������B
�@���b�g�ɁA��ԂŁA���`���H��H�ׂ�����ƁA�C���X���������傳��A��������BCAA�����i�Ɏ�荞�܂�Č������ATrp���]�֎�荞�܂�Ղ��Ȃ�A�]��Trp�Z�x���㏸���ATrp���獇��������Z���g�j���Z�x���㏸����B
�@���A�a���҂��A���a�ɂȂ郊�X�N�������i�Q�{�j�̂́A�C���X�����ɂ��BCAA�̍��i�֎�荞�݂��������ATrp���]�֎�荞�܂�ɂ����Ȃ�̂��A�@�������m��Ȃ��i�^���́A���i��BCAA��������A��������BCAA�Z�x��ቺ�����邱�ƂŁA�]���̐_�o�`�B������������Ǝv����j�B
�@�̍d�����҂ł́A�̑��ł̃A�~�m�_��ӂ��������A���i�ł̃A�~�m�_��ӂ����i���A��������BCAA�Z�x���������A�]����Phe�Z�x��Tyr�Z�x���A��������Ƃ����B
�@�d�NJ̉���A��㏞���̍d�ςɂ��A�̍זE���@�\�s�S�Ɋׂ�A�喬����Ȃ������s�H�����B���A�{���A�̑��ʼn�ł����ׂ��A�����Ǔ��̓Ő������i�A�����j�A�A�A�~���A�t�F�m�[���A�ዉ���b�_�j�Ȃǂ��A��z���璆���_�o�n�Ɉڍs����ƁA���_�_�o�Ǐ�������i�̐��]���j�B
�@���̂悤�ȏd�NJ̉����㏞���̍d���ɍۂ��āA�������̗V���A�~�m�_�́ABCAA�i���A�~�m�_�j���������AAAA�i�F�����A�~�m�_�j����������BBCAA��AAA�́A�]�ŁA���t�]�֖���Ĕ]���Ɉڍs����ۂɁA��������B�d�NJ̉����㏞���̍d�ςɍۂ��āABCAA���������AAAA����������ƁAAAA�́A�]���Ɉڍs���Ղ��Ȃ�ATyrosine�i�`���V���j����Octopamine���APhenylalanine�i�t�F�j���A���j���j�����-hydroxyphenyl ethanolamine���ATryptophan����Z���g�j���iSerotonine�j�����������B�����̕����́A�U���_�o�`�B�����Ƃ��āAnoradrenaline��adrenaline�ɑ����č�p���A�̐��]�ǂ̐��_�_�o�Ǐ�������B
�@�̍d�ςȂǂɂ��̐��]�ǂ𗈂��������҂́A�]���̃g���v�g�t�@���iTrp�j�ʂ������ɑ������Ă���B�̐��]�ǂł́A�����ɁA�_�o�`�B�����̃Z���g�j���i�g���v�g�t�@���������̍ޗ��ɂȂ�j���������A�����Ɗo�����A����t�]����BBCAA�i�g���v�g�t�@���Ɣ]���t�֖�̒ʉ߂���������j���܂ޗA�t�܂��A1�T�Ԓ��A�_�H����ƁABCAA���AAAA�i�g���v�g�t�@���Ȃǁj�Ƌ������āAAAA�̔]���t�֖傩��̔]���ւ̒ʉ߂�}�����A�_�o�`�B�����𐳏퉻���A�̐��]�ǂ����P����B �@�R�DBCAA�́A�A�����j�A�����ɕK�v�ȃO���^�~���_����������
�@�R�DBCAA�́A�A�����j�A�����ɕK�v�ȃO���^�~���_����������
�@BCAA�̃o�����́ABCAT�ibranched chain amino acid aminotransferase�FBCAA aminotransferase�j�Ƃ����y�f�ɂ��A��-�P�g�O���^���_�ɃA�~�m���]�ڂ����O���^�~���_�i���Q�j�����A���g�́A��-keto-isovalerate�i���P�g�_�FBCKA�j�ɂȂ�B
�@BCAT�FBCAA�{��-�P�g�O���^���_��BCKA�{�O���^�~���_
�@BCKA����́A�s���r���_�����������F�o�����A�C�\���C�V���̑�ӂ���́Apropionyl-CoA����������Asuccinyl-CoA���o�āA�s���r���_�����������B
�@�Ȃ��ABCAT�́ABCAA transaminase�Ƃ��Ă��B
�@�����ɂ́ABCAA���ӂ���BCAT�ƁAbranched-chain-ketoacid dehydrogenase���A���݂���B
�@BCAT�́A�r�^�~��B6�i�s���h�L�T�[�������_�A���R�j���A��y�f�Ƃ��ĕK�v�B��-keto-isovalerate�́ABCKDH�ibranched chain ��-keto acid dehydrogenase�j�Ƃ����y�f�ɂ��A�ى�����āA���̍ہANADH2+�����������BBCKDH�́A�^�����Ɋ����������B
�@�o��������́A�ŏI�I�ɂ́A�X�N�V�j��-CoA�isuccinyl-CoA�j�����������B
�@BCAA�̃��C�V����C�\���C�V���̈ى����A�ŏ��̒i�K�́A�o�����Ɠ��l�ɁABCAT��BCKDH�ɐG�}����A�O���^�~���_�����������i���S�j�B
�@BCAA���琶��������O���^�~���_�iGlu�j�́A�ؓ��i���i�j�ŁA�A�����j�A����ł���i�O���^�~�������������j�B
�@�O���^�~���_�iGlu�j�́A�]�A�̑��A�t���ŁA�A�����j�A�iNH3�j����������̂ɁA��ȃA�~�m�_�B
�@�O���^�~���_�́A�O���^�~�������y�f�iglutamine synthetase�j�ɂ��A�A�����j�A�ƌ������A�O���^�~���iGln�j�����������B
�@glutamine synthetase�F�O���^�~���_�{�A�����j�A���O���^�~��
�@�O���^�~���_�́AALT�iGPT�j�ɂ��A�s���r���_�ɁA�A�~�m���]������ƁA�������A�~�m�_�ł���A�A���j�������������B
�@ALT�iGPT�j�F�O���^�~���_�{�s���r���_����-�P�g�O���^���_�{�A���j��
�@�A���j���́A�̑��ŁA���V���ɗ��p����A�O���R�[�X����������A���t���ɋ��������B
�@�ؓ��i���i�j�ł́ABCAA����A�A���j����O���^�~�������������i�A���j���͊̑��ő�ӂ���A�O���^�~���͐t���ő�ӂ����j�B
�@�]�ł́ABCAA����A�O���^�~������������A�����ɕ��o�����i�O���^�~���͐t���ő�ӂ����j�B
�@�̑��ł́A���i�ȂǂŐ������ꂽ�A���j������A���V���ɂ��A�O���R�[�X�i�u�h�E���j�����������i���V���Ő��������O���R�[�X�̖�50���́A�A���j���̒Y�f���i���ޗ��ɗp������j�B�̑��́A�A�����j�A����荞��ŁA�A�f��r�����邪�A�i�喬�����Ɗ̐Ö������Łj�O���^�~���̔Z�x�́A�قƂ�Ǖω����Ȃ��B
�@���ǂł́A�O���^�~������A�A���j�������������B
�@�t���ł��A�O���^�~������A�A���j�������������i�A���j���͊̑��ő�ӂ����F���V���j�B
�@�]�⍜�i�ŁA�A�����j�A�iNH3�j�́A�O���^�~�������y�f�ɂ��A�O���^�~���_�iGlu�j�ƌ������āA�O���^�~���iGln�j�����������i���T�j�B
�@BCAA���A�̐��]�ǂ̊��҂ɁA�_�H��o���œ��^����ƁA�����A�����j�A�Z�x���ቺ����B
�@�ŋ߂́ABCAA���ܗL����A�~�m�_�������s�̂���Ă��邪�ABCAA���������Ă���l�ɂ́A�A�����j�A�̏��������߂āA�]�זE�̔�J�̉𑁂߂���ʂ����ҏo���邪�A���a�i�T�a�j�̊��҂ɂ́A�Z���g�j���Y����}������댯�͂Ȃ��̂��A�^��Ɏv����B
�@�S�D�����A�~�m�_�Z�x
�@�A�~�m�_�Z�x�i��mol/L�j�́A�������ƁA���t���̒l�́A���\�̔@���B
�@�o�����iVal�j�A���C�V���iLeu�j�A�C�\���C�V���iIle�j�A�g���I�j���iThr�j�A���`�I�j���iMet�j�A�t�F�j���A���j���iPhe�j�A�g���v�g�t�@���iTrp�j�A���W���iLys�j�́A�K�{�A�~�m�_�B�c���ł́A�q�X�`�W���iHis�j���A�K�{�A�~�m�_�B
�@�o�����iVal�j�A���C�V���iLeu�j�A�C�\���C�V���iIle�j�́A���A�~�m�_�iBCAA�j�B�t�F�j���A���j���iPhe�j�A�`���V���iTyr�j�A�g���v�g�t�@���iTrp�j�́A�F�����A�~�m�_�iAAA�j�B�̕s�S�i���NJ̉����㏞���̍d�ρj�ł́A�����A�~�m�_�Z�x���ω����āABCAA�iVal�ALeu�AIle�j�Z�x���ቺ���AAAA�iTyr�APhe�ATrp�j�Z�x��A���`�I�j���iMet�j�Z�x���A��������B
�@�\�Q�@�������A���t���̃A�~�m�_�Z�x �@�A�~�m�_ �@���� �@���t �@�_���A�~�m�_ �@�O���^�~���iGln�j �@596�`896 �@420�`580 �@�O���^�~���_�iGlu�j �@13�`61 �@4�`13 �@�A�X�p���M���_�iAsp�j �@��6 �@2�`6 �@�A�X�p���M���iAsn�j �@70�`140 �@��5 �@�����A�~�m�_ �@�A���j���iAla�j �@180�`528 �@12�`41 �@�o�����iVal�j �@152�`322 �@9�`20 �@���C�V���iLeu�j �@98�`180 �@3�`15 �@�C�\���C�V���iIle�j �@44�`105 �@1�`8 �@�O���V���iGly�j �@130�`326 �@3�`18 �@�Z�����iSer�j �@83�`196 �@15�`34 �@�g���I�j���iThr�j �@80�`207 �@21�`41 �@�V�X�e�C���iCys�j �@26�`71 �@��2 �@���`�I�j���iMet�j �@20�`44 �@��3 �@�t�F�j���A���j���iPhe�j �@45�`88 �@2�`9 �@�`���V���iTyr�j �@47�`96 �@5�`21 �@�g���v�g�t�@���iTrp�j �@37�`79 �@��3 �@����A�~�m�_ �@�q�X�`�W���iHis�j �@60�`124 �@6�`20 �@�A���M�j���iArg�j �@62�`149 �@12�`29 �@���W���iLys�j �@106�`288 �@10�`28 �@�I���j�`���iOrn�j �@32�`92 �@2�`8 �@�C�~�m�_ �@�v�������iPro�j �@109�`281 �@��3 �@��H���ɂ́A�����A�ؓ��i�ؑg�D�j����̃A�~�m�_���o����������B
�@�P���ȏ��H�������ƁA��������BCAA�́A��U�A�����ԑ�������i�C���X�����s���������j�B
�@����ɐ�H�������ƁABCAA�����߂Ƃ��Ėw�ǂ̃A�~�m�_�́A��������iGly��Thr�͌������Ȃ��j�B
�@�d�NJ����ǎ��ɂ́A��������BCAA�́A�G�l���M�[���Ƃ��ė��p���ꌸ�����APhe��Trp�����i�̕���f����������B
�@�\�R�@�������A�~�m�_�Z�x�̕ϓ��i�Q�l�������x�J�q�����̕\�Q�������ς����p�j �@������ �@�������A�~�m�_�Z�x �@�㏸ �@�ቺ �@�̎��� �@Phe�ATyr�ATrp�AMet�ASer�AGly �@Val�ALeu�AIle�iBCAA�j �@�t���� �@Arg�AAsp�ACit�i��K�{�A�~�m�_�j �@Val�ALeu�AIle�AThr�AHis�ATyr �@���C���X�������ǁi�C���X���m�[�}�j �@Ala �@Val�ALeu�AIle�ATyr�APhe�AMet �@��C���X�������ǁi���A�a�j �@Val�ALeu�AIle�APhe�ATyr �@Ala�AGly�AThr�ASer �@��`���h�{��ԁiKwashiorkor�j �@Ala �@Val�ALeu�AIle�AThr�ATyr�AMet�ALys �@�d�NJ����ǁi�s���ǁj �@Phe�ATyr �@Val�ALeu�AIle �@�A�~�m�_���ܓ��^ �@�e��A�~�m�_ �@ �@�o���v���_�i�g���E�����^ �@Gly�AGln �@Glu�AAsp�AMet�AIle �@���[�v���V���b�v�A�� �@Val�AIle�ALeu �@  �@�T�D�̎����p�o���h�{��
�@�T�D�̎����p�o���h�{��
�@AAA��`�I�j���́A��ɁA�̑��ő�ӂ���邪�ABCAA�́A�̑��ł͂قƂ�Ǒ�ӂ��ꂸ�A��Ƃ��āA���i�Ɣ]�ő�ӂ����B�̑��a�̐l�́A�i���b��S�������j���ނ⋛���A�iBCAA�𑽂��܂ށj�哤���i�A���A�����i��ۂ邱�Ƃ����߂��Ă���B
�@�̍d���̊��҂́A�̋@�\���ቺ���A�H���Őێ悷��`���ʂ�������ƁA�H����A�����j�A���㏸���A�̐��]�ǂ������N�����B
�@�H���Őێ悷��`���ʂ�}������Ɓi��`���H�j�A�A�����j�A�̏㏸�͗}�������i�̐��]�ǂ̔��ǂ͗}�������j���A��A���u�~�����ǂ����P�o���Ȃ��B
�@���̂悤�ȏꍇ�A��`���H�ɁABCAA��z�������̎����p�o���h�{���p����ƁA�A�����j�A�̏㏸��}�������܂܁A�`���ێ�ʂ̕s����₢�A�������`������A���u�~���l���A���P���邱�Ƃ��\�ƌ�����B
�@BCAA�́A���i��]�ő�ӂ���A���������O���^�~����A�A���j���́A���t����A������A�t���⏬���ŁA��ӂ����B
�@�̐��]�ǎ��ɂ́ABCAA���܂��ߏ�ɓ��^����ƁA���V�����s���Ȃ��ׁA���A���j�����ǂ𗈂����B�܂��A�A�����j�A���A�f��H�ŏ�������Ȃ��ׁA���O���^�~�����ǂ𗈂����B
�@�̎����p�o���h�{�܁iBCAA���܁j�Ƃ��ẮA�A�~�m���o��EN�A�w�p��ED�A���[�o�N�g�������A�̔�����Ă���B
�@�A�~�m���o��EN�ɂ́A�A���j�����܂܂�Ă��Ȃ��i�_�H�Ò��p�̃A�~�m���o���ɂ́A�A���j�����܂܂�Ă���j���A�w�p��ED�ɂ́A�A���j�����܂܂�Ă���B
�@���[�o�N�g�����́ABCAA�i���A�~�m�_�j�݂̂���Ȃ鐻�܂ł���A�{�܂݂̂ł́A�K�v�A�~�m�_�������Ƃ͏o���Ȃ��B
�@�H�i���t�B�b�V���[��i�H�i��BCAA/AAA��j�́A���H�ł�1.9�A���H�ł�3.6�A�����H�ł�4.8�ƌ�����F�����̕����AAAA�ɔ䂵�āA��葽����BCAA���A�܂�ł���i�H�i���̊܂܂��BCAA��AAA��mg��́A�\1�Ɏ������j�B
�@�̐��]�ǂ̃��f�����i�喬�ƐÖ����������C�k�FAAA��A�����j�A���܂ޖ喬�����A�̑����o�R���Ȃ��ŁA���ځA�]�ɉ��j�ɁA���H��^����ƁA���������́A����26���Ԃɉ߂��Ȃ��B�������A�̐��]�ǂ̃��f�����ɁA���H��^�����ꍇ�́A���������́A����54���Ԃɉ������A����ɁA�����H��^�����ꍇ�ɂ́A���������́A����69���Ԃɉ�������B �@�U�D���̑�
�@�U�D���̑�
�@�EBCAA�i���A�~�m�_�j�́A�`���������i��p�ƁA�`������}����p�i�ؒ`������}����p�j������B
�@�EBCAA��A���j���́A���ǂŐ�������A�i�喬�����j�̑��ɗA�������B�A���j���́A�ؓ��i���i�j��t���ł���������A�̑��ɗA�������i���V���ɗ��p�����j�B
�@BCAA�́A�̑����獜�i�ɗA�������B���i��BCAA���琶��������O���^�~���́A���ǂ�t���ɗA������A��v�ȉh�{�f�i�G�l���M�[���j�Ƃ��ė��p�����B
�@�EBCAA�́A�q�g�̌����K�{�A�~�m�_�̖�40�����߂�B
�@����BCAA�́A�ɓx�̒`�����R�i�A�~�m�_�ێ�ʒቺ�j�A�̏�Q�i�������p�̒ቺ�A�O���R�[�Q���~�ς̌����j�Ȃǂɂ���Č�������B���̍ہA�ؓ��i���i�j��BCAA�̏�����傷��i�G�l���M�[���Ƃ��ė��p�����j�B
�@�̏�Q�⊴���ǂɍۂ��ẮA�̑��ő�ӂ����F�����A�~�m�_�iAAA�FPhe��Tyr�Ȃǁj�͌����Z�x���㏸����B
�@�\�S�@C�^�̍d�ϊ��҂̌����A�~�m�_�l�i�Q�l�������J���������̕\�P�����ς����p�j �@�������� �@C�^�̍d�ρin��38�j �@����l �@�����l �@�����@ �@����l �@Fischer�� �@�@�P�D�V�X�}�O�D�V�V �@�� �@�@�Q�D�S�`�S�D�S �@BTR �@�@�@�R�D�P�}�P�D�T �@�� �@�@�S�D�S�`�P�O�D�O �@BCAA�inmol/mL�j �@�R�R�X�D�P�}�P�Q�T�D�R �@�� �@�@�Q�V�O�`�U�O�O �@Phe�inmol/mL�j �@�@�W�S�D�U�}�Q�V�D�O �@�� �@�@�@�S�R�`�V�U �@Tyr�inmol/mL�j �@�P�Q�P�D�P�}�R�W�D�W �@�� �@�@�@�S�O�`�X�O �@Met�inmol/mL�j �@�@�S�U�D�V�}�Q�W�D�R �@�� �@�@�@�P�X�`�S�O �@Phe/Tyr������ �@�@�O�D�V�P�}�O�D�P�R �@�� �@�O�D�W�S�`�P�D�O�V �@Alb�ig/dL�j �@�@�R�D�R�}�O�D�U �@�� �@�@�S�D�P�`�T�D�R �@Ch-E�i��ph�j �@�O�D�S�P�}�O�D�Q�S �@�� �@�@�O�D�U�`�P�D�R �@�A�����j�A�i��g/mL�j �@�W�P�D�O�}�Q�U�D�U �@�� �@�@�@�P�Q�`�U�U �@�������i/mm3�j �@�X�D�V�}�S�D�Q�~�P�O�R �@�� �@�P�R�}�R�U�~�P�O�R
�@�E���C���X�������ǂ́ABCAA�̍��i�i�ؒ`�����j�ւ̎�荞�݂�������i�A�����j�A�̉�ō�p�Ȃǂɗ��p�����j�̂ŁABCAA�̌����Z�x����������B
�@�E�H��100g������Ɋ܂܂��BCAA�ȂǁA�A�~�m�_�̗ʁimg�j�́A���L�̕\�̔@���B
�@�\���ŁAIle���C�\���C�V���ALeu�����C�V���AVal���o�����APhe���t�F�j���A���j���ATyr���`���V���AMet�����`�I�j���ACys���V�X�`���ALys�����W���ATrp���g���v�g�t�@���AArg���A���M�j���AAla���A���j���AAsp���A�X�p���M���_�AGlu���O���^�~���_�B
�@�\�T�@�H�i�H��100g������̃A�~�m�_�g���img/100g edible protein�j �@�H�i�� �@�`����
�@�ig�j�@���A�~�m�_�iBCAA�j �@�F�����A�~�m�_�iAAA�j �@�ܗ��A�~�m�_�iSAA�j
�@Lys
�@Trp
�@Arg
Ala
Asp
�@Glu�@Ile �@Leu �@Val �@���v �@Phe �@Tyr �@���v �@Met �@Cys �@���v �@�哤�i���j �@35.3 �@1800 �@2900 �@1800 �@6500 �@2000 �@1300 �@3300 �@ 560 �@ 610 �@1200 �@2400 �@ 490 �@2800 �@1600 �@4400 �@6600 �@�[�� �@16.5 �@ 760 �@1300 �@ 830 �@2890 �@ 870 �@ 680 �@1600 �@ 260 �@ 290 �@ 550 �@1100 �@ 240 �@ 940 �@ 680 �@1800 �@3200 �@�ؓ��i���[�X�j �@20.3 �@ 990 �@1700 �@1100 �@3790 �@ 820 �@ 700 �@1500 �@ 590 �@ 230 �@ 820 �@1800 �@ 250 �@1300 �@1200 �@2000 �@3200 �@�{���i�����j �@18.0 �@ 880 �@1500 �@ 920 �@3300 �@ 740 �@ 620 �@1400 �@ 530 �@ 220 �@ 750 �@1600 �@ 210 �@1200 �@1100 �@1800 �@2900 �@�H�����i���j �@20.6 �@ 950 �@1600 �@1100 �@3650 �@ 830 �@ 690 �@1500 �@ 660 �@ 230 �@ 890 �@1800 �@ 230 �@1200 �@1200 �@2000 �@2800 �@儁i���j �@ 6.8 �@ 300 �@ 460 �@ 360 �@1120 �@ 280 �@ 220 �@ 500 �@ 180 �@�@97 �@ 280 �@ 490 �@�@90 �@ 390 �@ 540 �@ 610 �@ 830 �@�āi�����āj �@ 6.8 �@ 290 �@ 570 �@ 430 �@1290 �@ 370 �@ 280 �@ 650 �@ 170 �@ 160 �@ 330 �@ 250 �@�@99 �@ 550 �@ 390 �@ 650 �@1300 �@�H�p�� �@ 8.4 �@ 340 �@ 660 �@ 400 �@1400 �@ 460 �@ 240 �@ 700 �@ 150 �@ 210 �@ 360 �@ 220 �@�@96 �@ 290 �@ 270 �@ 390 �@3100 �@
�@���܂�
�@�O���^�~���_�iglutamic acid�FGlu�A���́Aglutamate�j���O���^�~���iglutamine�FGln�j�̕ϊ��Ɋւ��āB
�@�P�j�D�O���^�~���_�f�q�h���Q�i�[�[
�@�O���^�~���_�́A�O���^�~���_�f�q�h���Q�i�[�[�i�O���^�~���_�E���f�y�f�Fglutamate dehydrogenase�FGDH�A�܂��́AGLDH�j�ɂ���āA�A�����j�A����-�P�g�O���^���_�i2-�I�L�\�O���^���_�j���琶�������B
�@�A�����j�A�iNH4+�j�{��-�P�g�O���^���_��L-�O���^�~���_�iGlu�j
�@GDH�i�O���^�~���_�E���f�y�f�j�́A�O���^�~���_��������ۂɂ́ANADP+���y�f�Ɏg�p���A�O���^�~���_���ى�����ۂɂ́ANAD+���g�p����iNADH2+�����������j�B
�@�A����ۂł́AGDH�ɂ��A�O���R�[�X�i��-�P�g�O���^���_�j�ƃA�����j�A����A���ʂ̃A�~�m�_�̍������\�B
�@GDH�̑啔���́A�̑����~�g�R���h���A���}�g���b�N�X�ɑ��݂���B
�@�Q�j�D�O���^�~�������y�f
�@�O���^�~�������y�f�iglutamine synthetase�FGS�j�́A�O���^�~���_�ƃA�����j�A�����������A�O���^�~���iGln�j������B
�@L-�O���^�~���_�iGlu�j�{�A�����j�A�iNH3+�j��L-�O���^�~���iGln�j
�@���̔����ɂ́AATP�AMg2+���K�v�B
�@���̔����́A���ɁA�]�ł̃A�����j�A�̉�ł�A�t���ł̃A�����j�A�r���ɁA�d�v�B
�@�O���^�~���_�ƃO���^�~���́A�O���^�~�������y�f���O���^�~�i�[�[�ɂ��A���݂ɕϊ������B
�@�R�j�D�O���^�~���_�����y�f
�@�O���^�~���́A�O���^�~���_�����y�f�iglutamate synthase�j�ɂ���āA��-�P�g�O���^���_�Ɣ������A�Q���q���O���^�~���_�ɕϊ������B
�@L-�O���^�~���iGln�j�{��-�P�g�O���^���_���QL-�O���^�~���_�iGlu�j
�@ ���̔������ANADH2+���A������B
�@�O���^�~���_�iGlu�j�ƃO���^�~���iGln�j�́A�������A�~�m�_�ł���A�~�g�R���h���A���ŁAm-AST�im-GOT�j�ɂ��A��-�P�g�O���^���_�i2-�I�L�\�O���^���_�j�ɂȂ�ATCA��H�i�N�G���_��H�j�ɓ���B
�@�g���v�g�t�@���iTrp�j�A�A���j���iAla�j�AAMP�Ȃǂ́A�O���^�~��������}������B
�@�A���j���AAMP�́Aglutamine synthetase�̊�����}������i��-�P�g�O���^���_��ߖāATAC��H���@�\������j�B
�@�Ȃ��A�A�����j�E���C�I���iNH4+�j�́A�]���t�֖��ʉ߂��ɂ������A�A�����j�A�iNH3�j�́A�]�_�o�זE���Ɉڍs���₷���B
�@���P�F�g���v�g�t�@���́A�K�{�A�~�m�_�̂ЂƂB
�@�g���v�g�t�@���́A���ށi�����āA�������j�A�哤�A���i�ؓ��Ȃǁj�A���i�A�W�Ȃǁj�A�{���A�����A��i�ق���Ȃǁj�A�����̐H�a�Ɋ܂܂�Ă���B
�@���ނ́A�Z���g�j���̌����ƂȂ�g���v�g�t�@���𑽂��܂ނ̂ŁA���a�̐l�́A���ނ�H�ׂ�Ɨǂ��ƌ����l�����邪�A�g���v�g�t�@���́A�哤�ȂǁA�����̐H�a������A�\���ɐێ�\�Ǝv����B
�@�g���v�g�t�@���́A���ށA�哤�ȊO�ɂ��A�S�}�A���Ԑ��A�����i�A�����A�Ԃ݂̋��Ȃǂɑ����܂܂�Ă���̂ŁA�����̐H�i�́A���a�ɗL�p��������Ȃ��B
�@���Q�F�O���^�~���_�́AALT�iGPT�j�ɂ��A�s���r���_�Ɣ������āA�A���j���ɕϊ������B
�@�O���^�~���_�i�g���E�� �iSodium Glutamate�j �́A���z�A�V�C�^�P�A���߂ȂǂɊ܂܂�A�u�����i�o���`�j�v�́u���ܖ��i�|�݁j�v�Ƃ��ėp�����ė����B
�@�q�g������́A�O���^�~���_�𑽂��܂�ł���B
�@�Ȃ��ABCAA�́A�^�����ɁA���i�ňى�����A�O���^�~���_�����������B���̃O���^�~���_�́A���Ő�����s���r���_�ɁAALT�iGPT�j�ɂ��A�A�~�m���]�ڂ����A�A���j���������A�̑��ł����V���𑣐i������ƍl������B
�@���R�F�����^�r�^�~��B6�́AWest�nj�Q�i�_���Ă�j�Ȃǂ́A����]�_�o�����̎��ÂɁA�p�����Ă���B
�@�_���Ă�̏Ǘ�i6�J���j���j�ŁA���t�����2�J���ԁA�G�R�[24�^�E�C���X����������i���t���̍זE�����A29/3/��l�`280/3/��l�ɑ������A��6�J���ԁA���������j�A����MRI-T2�����摜�ŁA�U�ݐ��̍��M���悪�F�߂��A�_���Ă�̔��ǂɁA�G���e���E�C���X�i�G�R�[24�^�E�C���X�j�ɂ��U�ݐ��J�����]�����֗^���Ă���Ƌ^��ꂽ�Ǘ������B
�@���S�F���C�V���́A�ŏI�I�ɂ́Aacetoacetate��acetyl-CoA�Ɉى������B
�@�C�\���C�V���́Aacetyl-CoA��propionyl-CoA�ɕ�������A��҂́Asuccinyl-CoA�ɂ܂ňى������B
�@���T�F�O���^�~���́A�����ŁA�O���^�~�i�[�[�ɂ�蕪������A�O���^�~���_�����������B
�@�����ł́A�O���^�~����A�O���^�~���_�́A��ӔR���Ƃ��āA�d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B
�@�O���^�~���_�́A�������ōł������A���j���ɕϊ������B
�@�Q�l����
�@�E�n�[�p�[�E�����w�i����14�ŁA�O�Y�`���Ė�A�ۑP������ЁA�@1975�N�j�D
�@�E���H�[�g��b�����w�i�������w���l�A��P�ő�S���A2003�N�j.
�@�E��؍h��A���F�z�[�g�������w�@��R�Łi�������w���l�A2005�N�A��3���j�D
�@�E���ȁ@61��6���i1988-6�j�@61:1105�D
�@�E�̎����@���{��t��G���@��92���E��7���@���a59�N�D
�@�E��{�k��A���F���t���G�R�[24�^�E�C���X���������ꂽ�����_�o�����̌����A���{�����Ȋw��G���A101��5���A909-915�A1997�N�D
�@�E����F�q�F�ܒ��H�i�����\�Q�O�O�T�i���q�h�{��w�o�ŕ��A2005�N�j�D
�@�E�����r���F�悭�킩��ŐV��w�@�V�Ŋ̑��a�A����16�N�i��w�̗F�Ёj�D
�@�E�x�J�q���F�����A�~�m�_�A�ŐV�@�Տ�������ABC�A���{��t��G���@��135���E���ʍ��i2�j�A���U����V���[�Y�|70�A����18�i2006�j�N10���DS172-S173�ŁD
�@�E�J�������A�������u�FQ17�@�A�~�m�_���͂ʼn����킩��́H�A�i�[�V���OQ&A�@�S�ȂɕK�v�ȉh�{�Ǘ�Q&A�A36-37�ŁA������w�Ёi2005�N�j�D
�@�E�J�������A�������u�F�����w�p�����[�^�[�F�`����ӁF�A�~�m�_���́A�Տ������A48 (9): 989-994�ŁA2004�D
�@�E�J�������A�������u�FQ35�@�̏�Q���̒`�����^�@�́H�A�i�[�V���OQ&A�@�S�ȂɕK�v�ȉh�{�Ǘ�Q&A�A74-75�ŁA������w�Ёi2005�N�j�D
�@�E�J�����N�FQ33�@�N�P���E�������̒`�����^���@�́H�A�i�[�V���OQ&A�@�S�ȂɕK�v�ȉh�{�Ǘ�Q&A�A70-71�ŁA������w�Ёi2005�N�j�D
�@�b�g�b�v�y�[�W�b�����ƌ����̊W�b�~�j��w�m���b�����w�̒m���b��w�̘b���b�����Ȏ����b�����̕s�v�c�b�����N�W�b