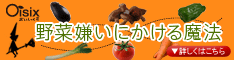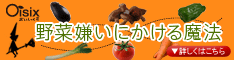



痒み
痒み(かゆみ、そう痒)は、肥満細胞(マスト細胞)やケラチノサイト(注1)から放出される、ヒスタミン、トリプテース(プロテアーゼの1種)、ロイコトリエンB4(LTB4)などによって、引き起こされる。
痒みには、一旦、皮膚に痒みが発生し、掻き壊すと、皮膚が刺激され、さらに痒みが増すと言う、痒みの悪循環がある(itch scratch cycle)。
1.ヒスタミン
真皮表層で、肥満細胞から放出されたヒスタミンは、C線維上のH1受容体(H1レセプター)を介して、中枢神経(脳)に、痒みを伝達する。H1受容体は、C線維のみならず、血管内皮細胞にも、存在する。
肥満細胞から放出されたヒスタミンは、痒みを伝達する以外に、紅斑を形成させたり(血管を拡張させる)、浮腫を生じさせたりする(血管透過性を亢進させる)。
2.サブスタンスP(SP)
痒みにより、皮膚の表皮が掻き壊される(掻破)刺激は、求心性にC線維を上行するが、一部の刺激は、同じC線維を逆行して、表皮のC線維末端(ポリモーダル受容器)から、サブスタンスP(SP:substance P)などの神経ペプチドを、放出させる。
表皮に遊離されたサブスタンスP(SP)は、血管内皮細胞の膜上に存在する、SPの主要受容体のNK-1R(neurokinin-1 receptor:注2)に結合し、血管を拡張させるので、紅斑が、形成される。表皮のサブスタンスP(SP)は、真皮表層の肥満細胞やケラチノサイトに作用して、ヒスタミン、LTB4などのメディエーターを遊離させ、サイトカインを放出させ、NOを産生させ、間接的に痒みを引き起こす。SPは、また、C線維のNK-1R(neurokinin-1 receptor)を介して、直接的にも痒みを引き起こす。
SPや肥満細胞由来因子の刺激により、隣接するC線維も刺激される。また、軸索反射が起こり、刺激が、C線維の別の分枝を逆行して、表皮のC線維末端(ポリモーダル受容器)から、サブスタンスP(SP)などの神経ペプチドが、放出される。
炎症時に産生される発痛物質(PGE2、ヒスタミン、ブラジキニンなど)は、ポリモーダル受容器の興奮性を、著しく高め、痛覚や、痒みに過敏にする。なお、ブラジキニンは、血液凝固に際して、生成されるが、肥満細胞は、B2受容体を持ち、ブラジキニンが結合すると、ヒスタミンやPAFが放出されので、血液凝固は、痒みを惹起する。
3.抗ヒスタミン薬
ヒスタミンに対する受容体(ヒスタミン受容体)は、H1、H2、H3、及び、H4の4種類が存在することが、知られている。
H1受容体は、血管内皮細胞や、知覚神経線維(C線維)に存在する。
ヒスタミンが、血管内皮細胞のH1受容体に結合すると、血管内皮細胞の間隙が広がって、血管透過性を亢進させ、蕁麻疹など膨疹を形成させる。

真皮表層で、肥満細胞から放出されたヒスタミンは、真皮で、C線維上のH1受容体に結合し、中枢神経(脳)に、痒み感覚を伝達する。
第一世代の抗ヒスタミン薬(古典的抗ヒスタミン薬)は、H1受容体へのヒスタミンの作用に拮抗して、抗ヒスタミン作用を示す。
古典的抗ヒスタミン薬は、眠気、めまい、倦怠感など、中枢神経系抑制作用を示す。また、緑内障、前立腺肥大症の患者には、使用してはならない(使用禁忌)。
H2受容体は、皮膚では、組織肥満細胞、ケラチノサイト、血管内皮細胞に存在する。古典的抗ヒスタミン薬は、肥満細胞に対しては、H2受容体を介して、ヒスタミン遊離を抑制する。
H3受容体は、神経組織に存在する(ヒスタミンの遊離を自己調節する)。
H4受容体は、好酸球などの免疫細胞に、存在する。
第二世代の抗ヒスタミン薬(抗アレルギー薬)は、肥満細胞から、ヒスタミンのみならず、ロイコトリエンC4(LTC4)、血小板活性化因子(PAF)などの、ケミカルメディエーターの遊離を抑制する作用がある(注3)。
表1 抗アレルギー剤の比較(添付文書を参考に作成)
| 商品名 |
アゼプチン |
アレギサール |
アレジオン |
アレロック |
オノン |
クラリチン |
ザジテン |
ジルテック |
シングレア |
ゼスラン |
セルテクト |
リザベン |
| 一般名 |
塩酸
アゼラスチン |
ペミロラスト
カリウム |
塩酸
エピナスチン |
塩酸
オロパタジン |
プランルカスト
水和物 |
ロラタジン |
フマル酸
ケトチフェン |
塩酸
セチリジン |
モンテルカスト |
メキタジン |
オキサトミド |
トラニラスト |
| 1日投与量 |
2〜4mg |
0.4mg/kg |
10〜20mg |
10mg |
450mga) |
10mg |
2mg |
10mg |
10mg |
12mg |
60mg |
300mgc) |
| 1日投与回数 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
| 投与時間 |
朝食後、就寝前 |
朝食後、就寝前 |
|
朝、就寝前 |
朝食後、夕食後 |
食後 |
朝食後、就寝前 |
就寝前 |
就寝前 |
|
朝、就寝前 |
|
| H1受容体拮抗作用 |
+ |
|
+ |
+ |
− |
+ |
+ |
+ |
− |
+ |
+ |
|
| LTC4拮抗作用 |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
±b) |
+ |
+ |
− |
| LTB4拮抗作用 |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
± |
|
|
|
| PAF拮抗作用 |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
| セロトニン拮抗作用 |
|
|
+ |
|
− |
|
+(5-HT2A) |
|
− |
+ |
+ |
− |
| ブラジキニン拮抗作用 |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
| ヒスタミン遊離抑制作用 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
| SRS‐A遊離抑制作用 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
| LTB4遊離抑制作用 |
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
| TXB2遊離抑制作用 |
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
| PAF遊離抑制作用 |
|
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
+ |
| PGD2遊離抑制作用 |
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
PGE2産生抑制 |
| ECP・EPX遊離抑制作用 |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| タキキニン遊離抑制作用 |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
| 気管支喘息 |
○ |
○ |
○(DSは×) |
− |
○ |
− |
|
− |
○ |
○ |
− |
○ |
| アレルギー性鼻炎 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
− |
○ |
○ |
○ |
| 蕁麻疹 |
○ |
− |
○ |
○ |
− |
○ |
|
○ |
− |
○ |
○ |
−c) |
a):オノン(プランルカスト水和物)の1日投与量450mgは、4カプセル(1回2カプセルを朝食後及び夕食後の2回内服する)。
オノンドライシロップ10%は、通常、小児には、ドライシロップとして70mg/kg/日(プランルカスト水和物として7mg/kg/日)を、朝食後及び夕食後の2回に分け、用時懸濁して内服する。オノンドライシロップ10%の1日最高用量は、ドライシロップとして100mg/kg/日(プランルカスト水和物として10mg/kg/日)とし、プランルカスト水和物の成人の通常用量である450mg/日(ドライシロップとして4.5g/日)を超えないこと(オノンドライシロップ10%の1日最高用量は、4.5g/日)。
b):シングレア(モンテルカストナトリウム:併売名キプレス錠剤)は、LTD4拮抗作用は+(LTD4の受容体結合を強力に阻害する)。シングレアは、システイニルロイコトリエン(CysLT1)受容体へのロイコトリエンD4(LTD4)の結合を抑制し、気管支のLTD4による収縮を競合的に阻害する。LTD4は、ヒスタミンより1,000倍強い気道平滑筋収縮作用があり、収縮が持続する。シングレアは、ヒスタミン、アラキドン酸、セロトニン、アセチルコリンによって誘発される気管支収縮を阻害(抑制)しない。シングレアは、小児用にシングレアチュアブル錠5が販売されている。6歳以上の小児は、シングレアチュアブル錠5を1日1回就寝前に内服する。シングレアのようなロイコトリエン拮抗剤(LT拮抗薬)を使用時に、Churg-Strauss症候群様の血管炎(末梢血の好酸球増加,好酸球浸潤をともなう壊死性血管炎や肉芽腫)を生じることがあるの、末梢血、好酸球数、しびれ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺の浸潤陰影などの血管炎症状が現れていないか注意が必要。
c):リザベンドライシロップは、通常、小児には、0.1g/kg/日(トラニラストとして5mg/kg/日)を3回に分け、用時懸濁して内服する。リザベン細粒は、通常、小児には、0.05g/kg/日(トラニラストとして5mg/kg)を3回に分け、経口投与する。
リザベン(トラニラスト製剤)は、アトピー性皮膚炎、ケロイド・肥厚性瘢痕に保険適応が承認されている。
リザベンは、肥満細胞からのk学伝達物質など(ヒスタミン、LTB4、LTC4、LTD4、PAF、PGD2、PGE2、活性酸素)の遊離(放出)を抑制する。リザベンは、繊維芽細胞やマクロファージからのTGF-β1の産生を抑制し、ケロイドや肥厚性瘢痕の進展を抑制する。 抗ヒスタミン剤(抗ヒスタミン薬)は、鎮咳作用がある。
抗ヒスタミン剤は、痒み止め(掻痒)目的で、投与される。
抗ヒスタミン剤の止痒効果は、薬剤によって、異なる。
抗ヒスタミン剤には、副作用として、鎮静作用(眠気だけでなく、認知機能検査に異常を来たす)が現れることがある。
非鎮静性の抗ヒスタミン剤としては、エビデンスが示されているのは、フェキソフェナジン(商品名:アレグラ)、ロタラジン(商品名:クラリチン)、セチリジン(商品名:ジルテック)がある。
第1世代の抗ヒスタミン剤は、副作用として、眠気が強く現れ易い。しかし、小児のアトピー性皮膚炎など、痒くて眠れない患者には、第1世代の抗ヒスタミン剤の眠気作用が、有効な場合がある。
非鎮静性で安全なのは、アレグラ、アレジオン、エバステル。 アゼプチン、ニポラジン、ジルテックは、次に(中等度)安全。
表2 第2世代抗ヒスタミン剤の比較(参考文献の幸野氏の表1を改変し引用)
| 商品名 |
アゼプチン |
アレギサール |
アレグラ |
アレジオン |
アレロック |
エバステル |
クラリチン |
ザジテン |
ジルテック |
ゼスラン |
セルテクト |
タリオン |
ダレン |
| 一般名 |
アゼラスチン |
ペミロラスト |
フェキソフェナジン |
エピナスチン |
オロパタジン |
エバスチン |
ロラタジン |
ケトチフェン |
セチリジン |
メキタジン |
オキサトミド |
ベボタスチン |
エメダスチン |
| 1日投与回数 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1ハ) |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 半減時間ロ) |
16.5 |
4.31 |
9.6 |
9.2 |
8.75 |
15.1 |
14.3 |
6.7 |
6.7 |
32.7 |
5.2 |
2.4 |
7.0 |
| 眠気発現(%) |
0.1〜5 |
<5% |
2.0 |
1.2 |
11.6 |
1.8 |
6.4 |
4.4 |
6.0 |
2.2 |
4.8 |
5.7 |
6.3 |
| 小児用製剤 |
− |
○ |
−イ) |
○ |
− |
− |
− |
○ |
−(DS有) |
○ |
○ |
− |
− |
| 小児適応 |
|
○(1歳〜) |
○イ) |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
|
妊婦への
投与 |
添付文書 |
有益性判断 |
禁 |
有益性判断 |
有益性判断 |
有益性判断 |
有益性判断 |
避ける |
有益性判断 |
有益性判断 |
(禁) |
禁 |
有益性判断 |
有益性判断 |
| FDA基準 |
C |
C |
C |
|
|
|
|
C |
B |
|
|
|
|
| 非鎮静性 |
|
|
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
|
|
|
| 自動車の運転従事 |
禁 |
記載無 |
記載無 |
注意 |
禁 |
注意 |
記載無 |
禁 |
禁 |
禁 |
禁 |
注意 |
禁 |
| 気管支喘息 |
○ |
○ |
− |
○(DSは×) |
− |
− |
− |
○ |
− |
○ |
− |
− |
− |
| アレルギー性鼻炎 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 蕁麻疹 |
○ |
− |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
イ):アレグラは、小児にも適応が承認されている。アレグラは、7歳以上12歳未満の小児には、30mg/1回を1日2回(60mg/日)、12歳以上の小児には、60mg/1回を1日2回(120mg/日)、経口投与する。アレグラ(フェキソフェナジン塩酸塩)は、エリスロマイシン、ケトコナゾールなどと併用すると、クリアランスの低下や吸収率の増加が起こり(P糖蛋白の阻害による)、血漿中濃度が約2倍に上昇してしまう(併用したエリスロマイシンなどの血中濃度は上昇しない)。
ロ):単回投与時のデータ。
ハ):セチリジン(ジルテック)は、成人では、1日1回、就寝前に内服するが、小児では(ジルテックドライシロップ、ジルテック錠5)、1日2回、朝食後及び就寝前に内服する。
抗ヒスタミン剤(抗ヒスタミン薬)は、第一世代と第二世代とに分類される。
第一世代の抗ヒスタミン剤は、中枢神経系の副作用を発現し易い。
第二世代の抗ヒスタミン剤は、H1受容体に対する選択性が高く、脳内移行性が低いと言われる。第二世代の抗ヒスタミン剤は、ケミカルメディエータ(化学伝達物質)遊離抑制作用も持っている。
4.その他
・NOは、痒みを増強させる。
・好酸球から放出されるECP(epsinophil cationic protein)は、C線維を直接刺激し、痒みを誘発する。
痒みは、皮膚の表皮と、真皮表層で、H1受容体などにより受容され、C線維により伝導され、中枢神経(脳)で、痒みとして認識される。
・オピオイドペプチド(β-エンドルフィンなど)は、脳内で、受容体を刺激して、痒みを認識させる。
β-エンドルフィンは、μ-レセプターと結合して、痒みを誘発し、ダイノルフィンは、κ-レセプターと結合して、痒みを抑制すると言う。
・糖尿病では、外陰部の掻痒症などの皮膚掻痒症が、良く見られる(糖尿病性皮膚掻痒症)。
・高齢になると、皮膚は、老化により萎縮し、皮脂の分泌が減少し、乾燥しやすい状態になる(老人性乾皮症)。そして、バリア機能の低下により、外部環境の刺激物質を通過させやすくなるので、痒いと感じやすくなる。
老人性乾皮症は、角層中のセラミダーゼの活性が、加齢と共に増加し、セラミド含量が低下し、皮膚の保湿機能が低下することが原因で、発症する。
・肝臓が悪いと、皮膚の痒み(肝性掻痒)を訴える患者が、多い。痒み(肝性掻痒)は、四肢や、体部に感じることが多く、外陰部に痒みを感じることは、例外的とされ、糖尿病性皮膚掻痒症とは、異なる。
痒みは、ビリルビンよりも、胆汁酸が、原因と考えられている。
肝臓が悪い(肝機能障害があると)、胆汁うっ滞(鬱滞)が起こり、血中胆汁酸が、皮膚に蓄積する。
皮膚に蓄積した胆汁酸は、直接的に、皮膚の知覚神経を脱分極させるか、あるいは、間接的に、蛋白分解酵素やヒスタミンの放出を促進させて、痒みを生じさせると考えられている(注4)。
・アトピー性皮膚炎では、痛み、熱、酸刺激も、痒みを惹起する。
・痒みには、一旦、皮膚に痒みが発生し、掻き壊すと、皮膚が刺激され、さらに痒みが増すと言う、痒みの悪循環がある(itch
scratch cycle)。
人間は、痒くても、抑制して(我慢して)、掻き壊すことを、止めるが、猫などの動物は、皮膚を掻き壊して、潰瘍を形成したり、化膿させて、死ぬまで、治らないことがある。
抗ヒスタミン剤を服用したり、皮膚を冷却したりなど、適切な加療をして、痒みを除去することは、痒みの悪循環を断つ為に、必要。
・一般的な痒み:肥満細胞は、抗原や化学物質により刺激され、ヒスタミンが放出され、C線維が刺激され、脳に神経刺激が伝達され、痒みを知覚する。
乾燥肌による痒み:乾燥肌では、皮膚の角層のバリア機能が低下し、外部からの刺激により、角層直下に伸びたC線維が刺激され、脳に神経刺激が伝達され、痒みを知覚する。
サブスタンスPを介する痒み:C線維は、外部から刺激されると、サブスタンスP(SP)を放出する。放出されたサブスタンスPにより肥満細胞が刺激され、ヒスタミンが放出され、C線維が刺激され、脳に神経刺激が伝達され、痒みを知覚する。
・ヒスタミンは、脳内では、神経伝達物質として、覚醒の増加、徐波睡眠の減少、学習と記憶の増加、自発運動量の増加、摂食活動の抑制、痙攣の抑制、ストレスによる興奮の抑制、などの作用を現す。
抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗剤)は、脳内に移行し、脳内のヒスタミン作用を阻害し、眠気などの副作用を現す。
脳内H1受容体占有率は、アレグラ(フェキソフェナジン)<アレジオン(エピナスチン)<エバステル(エバスチン)<アゼプチン(アゼラスチン)<ゼスラン(メキタジン)<ジルテック(セチリジン)<ポララミン(クロルフェニラミン)<セルテクト(オキサトミド)<ザジテン(ケトチフェン)の順に高いと言う。
注1:ケラチノサイト(keratinocyte:角化細胞)は、表皮の基底層にあり、セラミドを生成し、表皮の角化を司っている細胞。ケラチン細胞の内は、ケラチン線維で充満され、ケラチン細胞の外は、セラミドなどの角質細胞間脂質で充満され、皮脂腺から分泌される皮脂膜と共に、水分や物質が、外界へ通過することを、防止したり、外界からの刺激(機械的、化学的、物理的)から、防御する。セラミドなどの細胞間脂質は、角層の水分保持機能として、水分蒸発を抑制し、角層中の水分含有量を維持する。
ケラチノサイトは、細胞質内にメラニン顆粒を有しているが、メラニン顆粒は、メラノサイトに由来する。
注2:NK-1Rは、サブスタンスP(SP)の主要受容体であり、C線維上、血管内皮細胞、ケラチノサイト(表皮角化細胞)、肥満細胞(マスト細胞)、ランゲルハンス細胞、線維芽細胞にも、存在する。
注3:ケミカルメディエーターの遊離の抑制機序は、不明の点が多いが、Ca2+流入抑制、膜安定化、アラキドン酸の細胞内への動員抑制、などによると、考えられている。
アゼラスチンには、TNF-αなどのサイトカイン産生を抑制する作用がある。
エメダスチン、セチリジンなどには、サブスタンスP(SP)反応性を減弱させる作用や、好酸球の遊走を抑制する作用があると言う。
塩酸オロパタジン(アレロック錠)は、主に、選択的に、H1受容体(ヒスタミンH1受容体)に拮抗作用を示すが、ムスカリンM1受容体には、ほとんど作用しない。更に、化学伝達物質(ロイコトリエン、トロンボキサン、PAF等)の産生や、遊離を抑制する。また、神経伝達物質のタキキニン遊離を抑制する作用も有する。このような作用により、塩酸オロパタジン(アレロック錠)は、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑)に、効能が、承認されている。

注4:従来、皮膚に蓄積した胆汁酸が、直接的に、皮膚の神経終末を刺激し(知覚神経を脱分極させ)、痒み(肝性掻痒)が生じると、推定されていた。しかし、近年の研究には、皮膚表面の胆汁酸と、血中胆汁酸の値とは、相関しないと言う報告があり、胆汁酸が、直接、神経終末を刺激して、痒み(肝性掻痒)が、生じるとする説を、否定する意見も多いと言う。従って、胆汁酸は、間接的に、蛋白分解酵素やヒスタミンの放出を促進させて、痒みを生じさせるのかも知れない。
胆汁酸は、(大腸癌などの)発癌を促進する作用があると言う。高脂肪食を摂取すると、胆汁酸やステロイド代謝産物が増加し、これらの腸管内への排泄が増加し、発癌を促進させる恐れが考えられる。
参考文献
・かゆみとその対策:日本医師会雑誌 第132巻・第13号(2004年12月).
・富田文、野村和博:アトピー治療を見直す、Nikkei Medical、2006年10月号、65-71頁.
・高森健二:乾燥とかゆみ、きょうの健康、86-89頁、2005年11月号.
・中川秀己、谷内一彦:学童期のアトピー性皮膚炎患者に対する抗ヒスタミン薬の使用、アレルギーの臨床、57-64頁、2006年26巻11月号(通巻352号)、北隆館.
・吉田隆実:抗アレルギー薬、小児科、Vol.38 No.1、29-36頁、1997年.
|トップページ|脂質と血栓の関係|ミニ医学知識|生化学の知識|医学の話題|小児科疾患|生命の不思議|リンク集|