
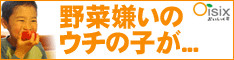
溶連菌感染症の扁桃腺所見
溶連菌感染症では、以下のように、咽頭や、扁桃腺や、口蓋に、特有な所見が現れることが多い。
・扁桃腺(口蓋扁桃)が腫れて、膿(滲出物)が付着する。
・咽頭や扁桃腺や口蓋が、著明に発赤する。
・口蓋粘膜に、出血性濾胞状口内疹が見られる。
小川英治先生(小川小児科医院)は、溶連菌性咽頭炎を、口蓋粘膜の出血性濾胞状口内疹を特徴とするSP型(Streptococcal
pharyngitis)と、扁桃腺に膿(滲出物)が付着することが特徴のT型(Tonsilitis
exsudativa:滲出性扁桃腺型)とに、分類された。
年少幼児例は、軽度のSP型の咽頭所見を示し、年長児は、T型の咽頭所見を示すことが多い。
3歳未満の小児では、溶連菌感染症であっても、溶連菌に特有な咽頭所見を呈さないこともある(咽頭後壁のリンパ濾胞が腫脹する場合が見られる)。
成人も、咽頭痛が主で、溶連菌に特有な咽頭所見を呈さないことが多いが、SP型の咽頭所見(出血性濾胞状口内疹)が軽度見られる場合もある。
幼児の場合、溶連菌による扁桃腺炎(咽頭炎)では、咽頭や扁桃腺は、著明に発赤し、扁桃腺は、腫大する。
扁桃腺の表面は、膿状の滲出物は多く見られないが、咽頭培養用の綿棒などでスワブすると、多量の黄色粘稠な膿が、付着することが多い(滲出性扁桃腺炎)。
膿痰状の後鼻漏が、後咽頭に垂れていることもある。口蓋垂(喉ちんこ)も浮腫性に発赤腫脹し、周囲の口蓋粘膜も発赤し、点状の赤い小隆起や、小出血斑が見られる(出血性濾胞状口内疹:SP型)。年長児の場合、扁桃腺表面の溝や皺に沿って、黄白色の膿が、充満していることが多い(滲出性扁桃炎:T型)。
1).SP型
扁桃腺の腫脹に加え、口蓋粘膜が著明に発赤し、出血性濾胞状口内疹(周囲が輪状に出血した小丘疹:Forschheimer's spots)が、多数現れる。

溶連菌性咽頭炎(SP型):小川小児科医院の小川英治先生の御許可を得て転載引用
出血性濾胞状口内疹(Forschheimer斑)は、濾胞(直径1mm以下の少し隆起した黄色の小丘疹)の周囲が、輪状に出血している。Forschheimer斑(濾胞様粘膜疹)は、54.2~20.6%の症例に認められる。出血班を伴なうForschheimer斑は、8.2%の症例に認められる。
出血性濾胞状口内疹の出現の程度は、症例によって異なり、広い範囲(軟口蓋全体)に現れる場合や、口蓋弓に沿って軽度現れる場合などがある。また、濾胞は増大しているが、周囲の出血性変化に乏しい場合もある(ASO値などが、最初から高値で、溶連菌再感染の症例などの場合)。

出血性濾胞状口内疹:小川小児科医院の小川英治先生の御好意で転載引用
咽頭も、咽頭後壁が著明に発赤し、リンパ濾胞(顆粒)が腫大する。
口蓋垂は、浮腫状に腫れ上がる。
扁桃腺も発赤腫脹するが、滲出物(膿)の量は、比較的、軽度のことが多い。綿棒などで、扁桃腺をスワブすると、少量、膿血性の滲出物が、付着する。
溶連菌感染症で、SP型の咽頭所見を呈する場合は、猩紅熱型の発疹が現れることが多い。
SP型の咽頭所見は、年少幼児に多く、年長児や、成人では、少ない。
有効な抗生剤を内服しても、2日間程度は、出血性濾胞状口内疹など、SP型の咽頭所見は、残っていることが多い。
溶連菌に再感染する度に、出血性濾胞状口内疹の現れる範囲が限局的になり(口蓋弓にのみ見られる)、咽頭や扁桃腺の発赤腫脹の程度が弱くなり、咽頭所見のみでは、溶連菌感染症と気付かれ難くなる。
2).T型
扁桃腺(口蓋扁桃)が、発赤腫脹して、膿(滲出物)が付着する(滲出性扁桃腺型)。
膿(滲出物)は、黄白色(黄色味を帯びた灰白色)で、粘稠性のことが多い。
膿(滲出物)は、点状、線状、すじ状、パッチ状など、症例によって、様々な形状に、付着する。
口蓋弓などに、SP型に見られる出血性濾胞状口内疹が、軽度、存在することもある。
口蓋垂の発赤腫脹や、咽頭後壁の発赤や、リンパ濾胞の増殖も、現れる(SP型より、軽度のことが多い)。
T型の咽頭所見は、年長児の溶連菌性咽頭炎に多く見られる(ASO値が高値を示し、溶連菌の再感染例や、キャリアー状態からの増悪例)。

溶連菌性咽頭炎(T型):小川小児科医院の小川英治先生の御許可を得て転載引用
溶連菌性扁桃腺炎とアデノウイルス性扁桃腺炎を比較すると、滲出物(膿)は、前者は、黄色粘稠で、綿棒に付着し易く、後者は、白色で、綿棒で剥離し辛い傾向がある。
溶連菌性咽頭炎は、強い発赤(beefy red)や、濾胞状口内疹(輪状、点状の出血を伴なった紅暈)や、滲出性扁桃腺炎が見られる。濾胞状口内疹は、口蓋垂や口蓋弓を中心に見られ(口蓋垂は発赤・腫脹する)、軟口蓋にも濾胞(輪状出血を伴なう小丘疹)が多数見られる。溶連菌性の滲出性扁桃腺炎は、黄色の滲出物(膿)が、微慢性に、付着している。溶連菌性の扁桃腺炎では、腺窩性扁桃炎の所見を呈し、扁桃腺表面の溝や皺に沿って、黄白色の膿が、充満していることもある(年長児)。
溶連菌性咽頭炎は、強い咽頭痛を伴なう。
溶連菌が原因で、咽頭炎を起こしていても、咽頭痛、鼻水、発熱の症状はあっても、滲出性扁桃腺炎、腺窩性扁桃炎、濾胞性口内疹の所見を呈しない場合もある(診断には、咽頭培養が必要)。溶連菌感染症で、扁桃腺に膿(膿栓)やべラークが見られる頻度は、30.0%に過ぎないとする報告がある。

成人の溶連菌性扁桃腺炎(自験例:扁桃腺炎に滲出物が付着し、口蓋に濾胞状口内疹が見られる)
溶連菌性咽頭炎(溶連菌性扁桃腺炎)では、咽頭や扁桃腺を綿棒でスワブすると、粘稠な薄い黄褐色の分泌物(後鼻漏:比較的無臭)が採取される。この分泌物を顕微鏡で観察すると、多数の白血球(好中球)が見られる。
溶連菌が起因菌の急性穿孔性中耳炎では、耳垂れ液は、膿性と言うより、淡黄色の漿液性であることが多い(血液が混入することがある)。
3).口蓋垂の腫脹
溶連菌が原因の扁桃腺炎や咽頭炎では、口蓋垂(喉ちんこ:ノドチンコ)が、著しく腫脹し、発赤や痛みが見られることがある。扁桃腺は、必ずしも腫大しない。
 溶連菌による口蓋垂の腫脹(18歳男児例)
溶連菌による口蓋垂の腫脹(18歳男児例)
表1 滲出性扁桃腺炎を来たす疾患の鑑別
| 疾患名 |
原因ウイルス |
扁桃腺の滲出物 |
咽頭後壁のリンパ濾胞 |
口内炎 |
歯肉炎 |
頚部リンパ
節腫脹 |
| 形状 |
色 |
増殖 |
潰瘍形成 |
| 咽頭結膜熱 |
アデノウイルス |
膜(厚) |
白 |
+++ |
-~+ |
- |
- |
+ |
| 伝染性単核球症 |
EBウイルス |
膜、線 |
白 |
+~- |
- |
- |
- |
+++ |
| ヘルパンギーナ |
エンテロウイルス |
点、膜 |
白色 |
+~- |
- |
+ |
- |
- |
| ヘルペス性歯肉口内炎 |
単純ヘルペスウイルス |
膜 |
白~白黄 |
++ |
++ |
+ |
+ |
++ |
| 溶連菌感染症(猩紅熱) |
A群β溶血性連鎖球菌 |
微慢性、線 |
黄白~白 |
-~+ |
- |
- |
- |
++ |
参考文献
・小川英治、小川婦美子、金子克、本田寿子:目でみる小児科 溶連菌性咽頭炎、小児科、第24巻・第2号、巻頭(1983年).
・小川英治:図譜 小児感染症口内咽頭所見 その1 溶連菌感染症、日本小児科医会会報、No.13、113-120、1997年.
・小川英治:口を診る 小児感染症の口内所見 診断の決定的手掛かりになる例も、NIKKEI
MEDICAL、108-111頁、1988年8月10日号.
・伊東裕:風疹の口内疹写真 診断の手掛かりのひとつに、NIKKEI MEDICAL、62-64頁、1985年7月10日号.
・大国寿土、留目優子、山本隆彰:リウマチ熱の病因についての知見 小児内科 Vol.17 No.3、365-374、1985年.
・中沢秀夫、他:溶連菌感染症 最近の猩紅熱、小児科、Vol.20 No.10、1039-1049頁、1979年.
・岩崎恵美子:A群溶血性レンサ球菌感染症、感染症の診断・治療ガイドライン2004、日本医師会雑誌 臨時増刊、第132巻・第12号、230-231、2004年.
・岩崎恵美子:劇症型A群溶血性レンサ球菌感染症、感染症の診断・治療ガイドライン2004、日本医師会雑誌 臨時増刊、第132巻・第12号、202-205、2004年.
・城宏輔:細菌感染症(寄生虫を含む) 溶連菌感染症、実践小児診療、日本医師会雑誌 特別号、Vol.129 No.12、S205-207、平成15年(2003年).
・市橋保雄、他:急性伝染性疾患 猩紅熱、小児科学、791-792頁、1975年第3版(医学書院、1960年第1版発行).
・木村三生夫、柳下徳雄:カラー図説 発疹症、1982年第1版第3刷(東京医学社、1978年第1版第1刷発行).
・雪下國雄:感染症法に基づく医師の届出基準、日本医師会(平成18年3月20日、発行).
・山田俊彦:レンサ球菌の分類とその特徴、小児内科、Vol.21 No.6、813-816、1989年.
・中島邦夫:A群レンサ球菌感染症の疫学、小児内科、Vol.21 No.6、821-829、1989年.
・留目優子、大国寿土:A群レンサ球菌の菌体成分とその抗体、小児内科、Vol.21
No.6、835-841、1989年.
・勝亦慶人、河村修、古沢信行:レンサ球菌感染症-急性糸球体腎炎、小児内科、Vol.21
No.6、857-862、1989年.
・渡辺言夫:レンサ球菌感染症-リウマチ熱、小児内科、Vol.21 No.6、863-866、1989年.
・小林登、他:細菌感染症 3.連鎖球菌感染症、新小児医学体系 第20巻D、小児感染病学IV、35-62頁、1984年(中山書店).
・リウマチ熱、リウマチ入門 第10版[日本語版]、296-301頁、日本リウマチ学会編集(萬有製薬株式会社発行、1996年).
・飯田廣夫:連鎖球菌、感染症、62-78頁、理工学社(1981年).
・河合忠、本間光夫:感染・アレルギー・免疫病学、医学書院(1978年第1版第1刷).
・濱田義文、濱田文彦:感染症サーベイランスの中でみた病原体に基づく感染症の臨床、大塚薬報、2007/NO.622、27-32頁.
・佐久間孝久:アトラスさくま(小児咽頭所見 ATLAS SAKUMA)、2005年8月第1版第1刷発行(2006年5月第1版第3刷)、株式会社メディカル情報センター.
・James Todd: Streptococcal infections, Nelson Textbook of Pediatrics
(15th Edition), 750-754.
・James Todd: Rheumatic Fever, Nelson Textbook of Pediatrics (15th Edition),
754-760.
・Gary L. Darmstadt, et al: Cutaneous Bacterial Infections Impetigo,
Nelson Textbook of Pediatrics (15th Edition), 1890-1890.
|トップページ|脂質と血栓の関係|ミニ医学知識|生化学の知識|医学の話題|小児科疾患|生命の不思議|リンク集|


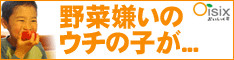

溶連菌による口蓋垂の腫脹(18歳男児例)
