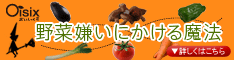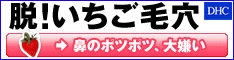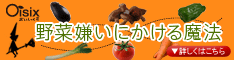

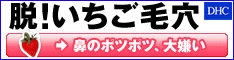


血液が固まりやすくなる時
以下のような時、血液は固まりやすくなり、血栓ができやすくなると考えられます。
・カゼなどで体内に炎症が起きた時:血管内皮細胞が活性化され、血液凝固が促進されたり、血管内皮細胞が障害され、血液が濃縮し、微小循環が停滞する。好中球やマクロファージに存在する、NADPH酸化酵素(NADPHオキシダーゼ)により、活性酸素のスーパーオキシドが産生される
・早朝(血小板凝集や血液凝固能は、日内変動する。心筋梗塞や脳卒中の発作は、早朝から起床後3時間以内に多い。)
・脂肪を過食した時
・砂糖を過食した時(血小板が、偽足を出して、活性化される)
・肉を過食した時(アラキドン酸が、血小板を小板凝集凝集させる)
・精神的ストレスや肉体的ストレスがある時
・罪悪感を抱いた時
・興奮した時(アドレナリンは、白血球や血小板を凝集させる)
・激しい運動
・熱射病(体温が2度上昇すると、血小板が偽足を出して凝集しやすくなったり、血栓が出来易くなる)
・高血圧症(血管が収縮して、血液の流動性が低下する)
・糖尿病
・喫煙
・妊娠
・ステロイドホルモンの服用
・ピルの服用
・膠原病
・抗リン脂質抗体症候群
・歯周病(炎症により、TNF-αが産生され、血栓が作られ易くなる)
・下痢や嘔吐による脱水(血液が濃厚になる)
・メタボリックシンドローム
注1:高温の環境によって引き起こされる熱中症は、熱痙攣(発汗による、Naの欠乏が原因)、熱疲労(発汗による、Naと水分の欠乏による脱水が原因)、熱射病(発汗の停止による体温の上昇)に、分類される。なお、炎天下で、直射日光を浴びて起こった熱射病は、日射病と呼ばれる。
生体は、高温の環境では、中枢性(脳の視床下部)の体温を維持する機構が作動し、皮膚血管を拡張させ、また、発汗による気化熱により、体内の熱を体外に放散させようとする。発汗により、水分や、Na(ナトリウム)、K、Ca、Mgなどのミネラルや、乳酸、アンモニア、尿素などが、体外に、排泄される。しかし、発汗により、Naや水分が欠乏し、脱水により、循環機能が低下すると、脳は、水・電解質調節を維持する為、発汗を停止させる。そうすると、中枢性に体温を維持する機構が作動しなくなり、体温が上昇し、熱射病になる。
発汗により、高温の環境でも、体温の上昇が抑制されるが、体内の水分やミネラル(Naなど)が欠乏していると、循環障害による疲労感、吐き気、眩暈などの症状(熱疲労)が現れたり、また、発汗が適切に出来ず、体熱が体内に籠もって、体温が40℃以上に上昇し、意識が混濁したり、呼吸停止により死に至ることもある(熱射病)。
熱射病では、応急処置として、風通しの良い日陰で(入手可能であれば、冷水や氷で体を冷やす)、足を高くして寝かせ、スポーツドリンクなどで、水分と塩分(NaCl)を、飲ませる。
発汗が多くなると、水や電解質が喪失し、脱水により、血液が濃くなる(ドロドロ血液)。さらに、発汗が不十分で、体温が上昇し40℃を超えると、血小板に突起(偽足)が生じ、血小板が凝集し易くなり、血栓が、出来易くなり(血液が固まり易くなり)、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まる。
発汗の機構は、まず、皮膚の真皮で、汗腺周囲の毛細血管から、血液中の水分やNaが漏出し、次に、汗腺で、体に必要なNaなどのミネラルの一部を再吸収し、残りを、汗として、体外に排泄する。病後などで、発汗機能が低下している人は、汗腺でのNa再吸収が低下し、汗のNa濃度が高くなり、発汗によるNa喪失量が、増加する。その為、病後など、体力が低下している人は、粒が大きい「玉の汗」が出るが、粘性が高く、蒸発しにくい。そのような場合、レシチンを含む食品(豆腐など)を摂取すると良いと言う。
|トップページ|脂質と血栓の関係|ミニ医学知識|生化学の知識|医学の話題|小児科疾患|生命の不思議|リンク集|